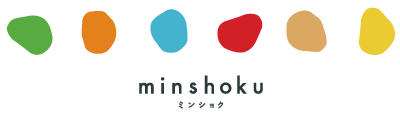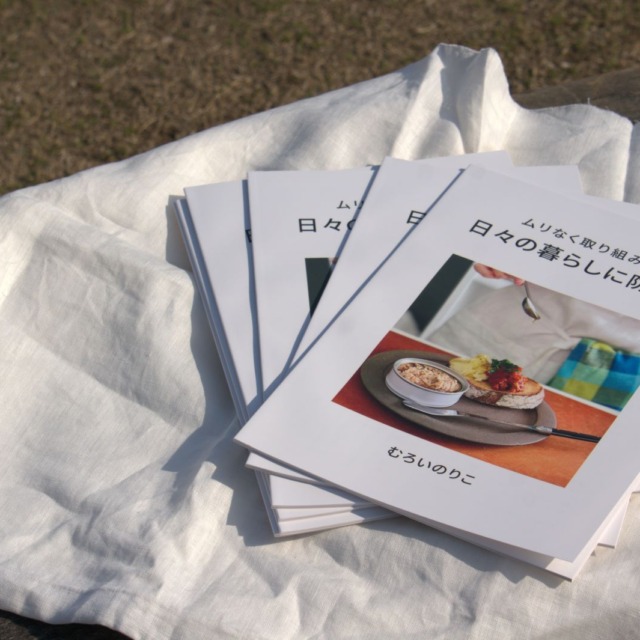記事一覧
記事一覧
ミンショクスタッフの記事一覧

ミンショク正式版オープン!

【予防が大切!】骨の健康を維持するために

【季節の変わり目】体調不良に要注意

【食欲を満たす】秋の栄養溢れる手作りおやつ

【行事食】秋到来!9月の行事食のススメ

【熱中症だけじゃない!】夏の冷え性対策
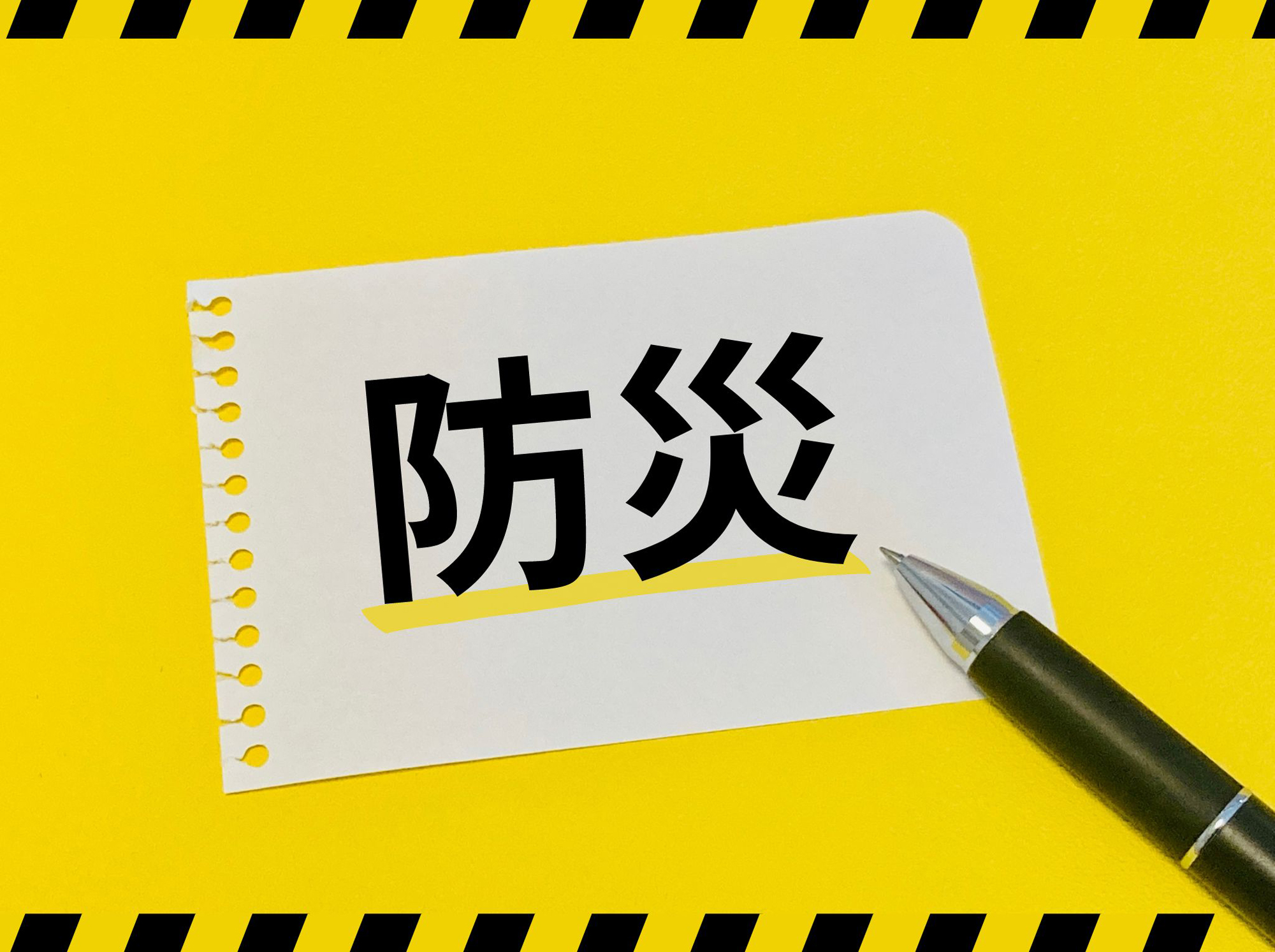
【災害時のお食事】クックチル食品は防災食としても大活躍

【ちょい足し食材】たんぱく質の補給におすすめ

【免疫力の維持・向上】食事を楽しみ心身ともに健康を保ちましょう